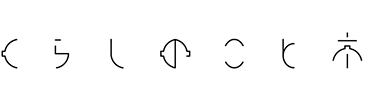 くらしにエッセイ
今日もお茶をいれる
 湯を湯呑みに八分目まで入れ、湯呑みを温めながら、湯冷ましをする。その間に茶匙で茶葉を一杯すくって急須に入れ、続いて湯冷ましをした湯を入れる。急須の中の茶葉が開いたら、いち、に、いち、に、のリズムで均等に濃淡のないように廻し注ぎ、絞りきる。 注がれる間にだんだんと緑色が濃くなり、ふっとお茶の香りがする。その瞬間が好き。 温かいお茶を飲むと固くなった脳がほぐれるように緩むのがわかる。お茶を飲んでほっとすることは、やはり日本人であり静岡県人だなと思う。 お茶請けにはあんこのお菓子がもちろん合うけれど、お茶にチョコレートも好きな組み合わせ。 冬の寒さが和らいで、日差しが春らしくなると私はそわそわし始める。そして、県内ニュースの天気予報で「遅霜予報」(おそじもよほう)が始まると、ますます気持ちが高まる。いよいよ新茶シーズン。 遅霜予報は、暖かくなった4月頃に茶の産地に霜が降りることを予報する。冬の寒い時期は寒さに耐えられるように葉が硬くなっているが、気温が上がり、成長したやわらかな新芽に霜が当ると、品質に影響を受けやすい。私にとって遅霜予報が始まることは、「まだまだ油断は禁物です」と警告をしつつ、「新茶まであともう少しだよ!」と教えてくれるもの。 暖かい日は、新芽が太陽の光を浴びてぐんぐんと伸びている様子を想像する。しかし、晴れの日が長く続くと、雨量が少ないのではないかと心配になる。1日、1日の天気によって期待と不安でぐるぐるとかき乱されながら新茶を待ちわびている。  祖母の家がお茶の小売店を営んでいる。 祖母の家がお茶の小売店を営んでいる。新茶を販売する前の試飲会に混ぜてもらった時に初めて新茶を飲んだ。新茶はごくごくと飲むものではなく、少量をたのしむもの。初夏の太陽に照らされ、新芽がきらきらと眩しくて、摘むのが勿体無いといつも眺めている茶畑の新緑が小さな湯呑の中にあった。みんなで口に入れ、ひと呼吸して店主の祖母が「じゃあ、今年はこれでいこう」と言ってそれぞれが仕事に掛かった中、私はひとり取り残されて、空っぽになった湯呑みをじっと見つめていた。 いつものお茶とは違うさわやかでみるい味(「みるい」とは静岡の方言で「未熟」や「若い」という意味。茶業者が茶の状態を表現する専門用語として、全国で「柔らかい」などの意味としても「みるい」が用いられている)、ちょっぴりしか淹れてもらえず少量をたのしむということが理解できない不満足感…当時は新茶を飲むこと自体が大人のすることのように思えた。 それから社会人になるまで新茶を口にすることはなかった。今となっては、10年分の新茶を無駄にしてきたとさえ思う。 昔から新茶は季節のご挨拶として贈る習慣がある。 新茶が出来上がると友人に贈るのだが、どうやら喜んでくれているのはご両親のようだ。私たちの世代がお茶を飲まなかったら、この先お茶に関わっている人たちはどうなってしまうのだろう。 私は、外出する際に、急須で水筒にお茶を淹れて持って出掛ける。理由は、自動販売機で買うより自分で淹れた方が断然おいしいから。 家庭で急須を使う人が減っているから、急須を作る職人が減っている。 茶を飲む人が減っているから、茶農家が減っている。 茶農家が減っているから、茶畑が… また来年も、この先も、新緑溢れる風景を静岡で見たいと願う。
|
||||||||||||||||